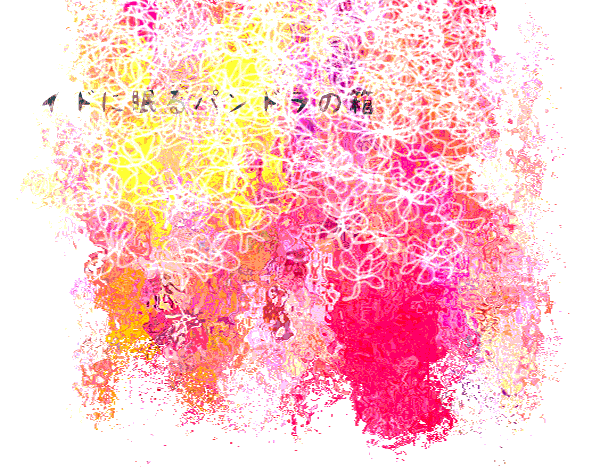
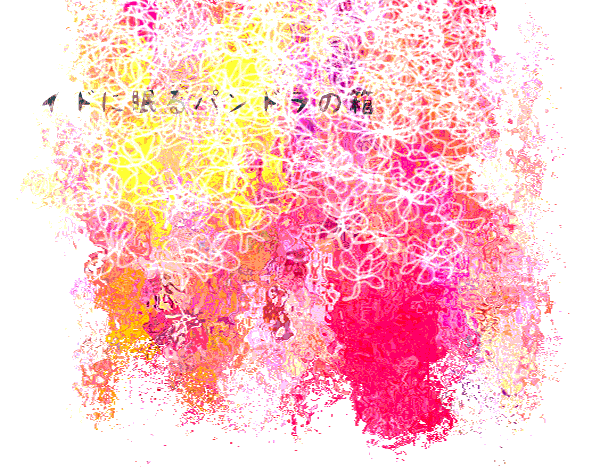
目の前に居るのは鉢屋三郎。 三年ろ組の不破雷蔵の顔をしているが、それは借り物の顔。 本当の彼の顔は誰も知らない。先生たちも、先輩も、もしかしたら同室で今彼の顔となっている不破雷蔵だけは別かもしれないけれど、それを俺が知るすべはない。 そんな彼と、彼の顔である不破雷蔵にたまたま庭先で居合わせて今に至る。 他愛もなくこの間の課題はどうだの、実習先の事件など、彼と同じ顔の不破が此方の会話にあまり興味がなさそうにしてボーっとしているのを尻目に見ながら会話は続く。 実のところ、俺の中で鉢屋三郎との会話は楽しいと思える部類に入る。 彼は話題も豊富に持ち、また話術も巧みで、彼の口から紡がれる言葉はひとつひとつが新鮮で艶やかに生き生きとしている。 同級生と話をしていても、どこか話がずれてしまうような疎外感を感じていたが、鉢屋と言葉を交わすときはそれがない。彼は稀有な存在だった。 不意に、話題が途切れた奇妙な間。三郎が、ふと口を噤み一瞬何か思考するかのような仕草を見せて、こちらが疑問に思う間もなく彼は何事か決断したようで、先ほどまでとは若干違った雰囲気を纏い、ゆっくりと口を開いた。 「久々知はいつも澄ました色の後ろに仏頂面を潜ませたような顔をしているな」 人の悪そうな笑みで口の端を吊り上げた鉢屋が俺を見据える。 思わず顔の表情が無になってしまい、これでは無言で肯定しているようなものではないか?と自問自答してみるが、答えは出ない。 「なぁ、どうして久々知は優等生を演じているんだ?」 「なに、を」 コツン、と何かが心の壁にぶつかった。 それは鉢屋の言の葉か、それとも此方を見据える双眸の眼光か。 「まるで優秀であることが己の存在意義のように」 どくん、と鉢屋の口から紡がれる音に秘められた趣旨が、目に見えぬ矢となって此方の心の臓へと突き刺さる。至るところから痺れるような痛みが漏れ出して、俺を追いつめて行く。 「我武者羅に足掻いて、必死に優れた自分を作り上げて」 どくんどくん、と鼓膜の隣に心臓があるのではないかと思ってしまうほど、うるさく鳴り響く己の心音。 「周りの同級生を心の底では見下して、自分が優秀なんだと優越感に満足している」 「…めろ」 「底なし沼に囚われ、息苦しくて、空気を求め、もがいているかのようだ」 「やめろっ」 震えだしそうな身体で絞り出された声音。 ボロボロの音はちっぽけな姿で俺の意思を具現するが、鉢屋はそれを無視して続けた。 「そうでもしなければ、自分を見失いそうで怖いか――久々知兵助」 サッと視界が黒くなり、次いで白くなる。 気づけば鉢屋が倒れていた。 俺の利き腕の拳は熱を持ちじんわりと痛んでいた。 「あ、……」 俺は鉢屋を殴り飛ばしてしまっていた。 踏み込んだ足と、感触がまだ残る拳。 鉢屋を殴ってしまったことを自覚した途端、先ほどまで騒がしかった心臓がサァっと冷え萎むかのようだった。 心の中では、鉢屋を殴ってしまったことで後悔や不安、恐れなどがぐるぐると止めどなく蠢いている。 そんな俺に、殴られたはずの鉢屋は怒るわけでも怖がることもせず、逆に不自然なほど清々しい笑みを浮かべて「怒った、な」と楽しそうに言うではないか。 鉢屋の反応は俺にとって予想外だった。 今までの経験上考えられない出来事で、俺は混乱していた。 そして俺は気づくと、殴ったことの謝罪もせず鉢屋から逃げ出すようにその場から駈け出して、体力配分など全く考えもしていない無茶な全速力で行くあてもなく無我夢中に足を動かし駆けだしていた。 |
|
090718 |