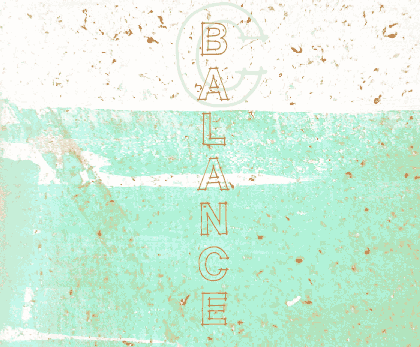
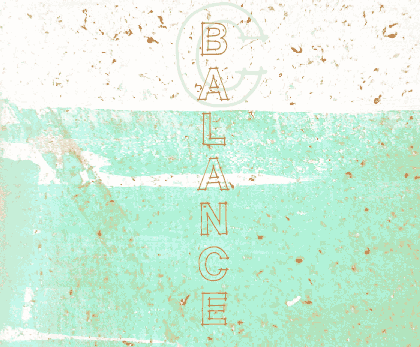
それは気まぐれだった。 何故その場に足を運んだのか――と、問われれば彼、鉢屋三郎はそう答えたに違いない。 「なんだ……これ」 三郎の前に広がる林の木陰に意図的に積まれたであろう石の山である。手のひらほどの岩の上に少し小さめな石を乗せて作られている山が(時々崩れてただの石の集合体になり変わっているものもあったが)一つ二つと言わずにそこら一帯を埋めるかのようにして存在していた。 鉢屋がそれらに目を向けたのは、一概に不可思議な光景だったというだけではなく、ひときわ彼の興味を引いたのはその異様な光景に鉢屋が見ることが出来る“穢れ”の残滓を見たからである。 弱々しく消えそうで消えないむしろ“穢れ”と呼ぶには悪質でもなく、けれどその存在は異質であり、鉢屋は初めて見るそれに興味を引かれ、しかし近付くことはせずにジッと遠目に観察をしていた。 「墓さ」 突然、鉢屋の背後から声が上がる。 あまりにもそれに興味を向けすぎた鉢屋はその声の主の気配にも気がつくことが出来ず、当然、突然湧いて出た言葉に驚き慄いた。 「立花先輩」 慌てて振り返った鉢屋の視線の先には、緑の木々の狭間から笑みを浮かべているひとつ上の学年に所属する立花仙蔵が居た。 彼は鉢屋の驚きようにさして気にする素振りを見せずに、静かに鉢屋の隣に歩み寄り先ほどまで鉢屋が眺めていたそれらを眺め再度口を開いた。 「それをなんだと尋ねただろう?それは墓だぞ鉢屋」 「墓…」 「私が殺した動物の墓だ」 彼は昼に何を食べたのかを言うかのような気さくさでその言葉を紡いだ。 言葉を木陰に溶かすように発する立花の姿を視野の中央で捉えながら、鉢屋は歩む彼の姿を唯一曝け出している鉢屋の生身である瞳でゆっくり追いかける。 「大半は私ではなくどこかの会計委員が作ったものだが」 立花は失笑を濁しながら膝を折り地面に手を伸ばす。 彼の白い指先がつまみ上げたのは小さな石。積み上げていたものが風か雨か、なんらかの原因で崩れ落ちたのであろうその一つを拾い上げ彼はそれを最初に作られていたであろう形に戻した。 崩れていた墓が元に戻ったことに満足したのか、そこから立ち上っていた軽薄な“穢れ”が尾を引っ込めて萎んでいく。 「先輩が殺した――って、この数をですか」 「そうだ」 鉢屋は立花の短い返答に黙った。 彼の脳内では様々な思考が巡っていたが、その最もがこれだけの数の生物を殺したというのに立花仙蔵が祟られていないという事実に対する疑問だった。 生きる物を殺せばそれだけ怨念がこの世に残るはずなのに、その矛先となるはずの立花仙蔵に“穢れ”はとり付いていない。 墓をつくり供養しているからかと思いもしたが、それにしたって残り滓ぐらい憑いてそうなのにそれすらもない立花の姿に鉢屋は首を傾げ唸りを上げた。 「最初に墓を作ったのはあの猫だ」 その言葉に鉢屋が思考に沈んでいた意識も持ち上げて立花の姿を見る。 しゃがんだ男の背中を眺めながら、鉢屋はざわりと辺りに散っている“穢れ”の残骸が騒ぐ音を聞いた。 「お前が私に墓を作れと言った臓物を散らして無様に死んでいたあの猫だよ」 そこで鉢屋は静かに押し黙った。立花仙蔵の、鉢屋を探る様子を隠そうともしない双眸の前に立ちつくす。 「覚えていないか?結局私はお前の忠告も聞かずやはり火薬で動物たちを殺傷した――首を折るのは手に感触が残って不快だし、クナイで首を掻っ切るのは呆気なさすぎる」 鉢屋の反応に仙蔵が肩をすくめ、失笑を零しながらそう言う。そこでようやく鉢屋は自身の記憶の貯蔵庫の奥の奥に転がっていたひとつの映像を引っ張り出し合点がついた。 立花の言葉に三郎の頭には幾年か前の映像が霞みがかって再生される。確かに彼が言葉で紡ぐように、あの時、忍術学園へ入学するために養父に連れられやってきた鉢屋はこの場所で一人の子供と出会っていた。 「やはり火薬がいい。臓物が爆し焦げる臭いはこの世が地獄だと痛感させる」 そう言って仙蔵は鉢屋の方へ妖艶な笑みをひとつ零して見せた。恐らく鉢屋が目を見開いて驚いた顔を浮かべていたことで、鉢屋がその時のことを思い出したのだと察したのだろう。 鉢屋は文字通り驚いていた。理由は至極簡単で、立花仙蔵がいつぞやの子供であったこと、すっかりその時のことなど忘れていた鉢屋に反して立花は覚えていたこと。そしてなによりあの時の鉢屋が、まだ不破雷蔵の顔をして居なかったというのに立花仙蔵があの子供を鉢屋三郎であると言い当てたことである。 「――趣味の悪さは変わっていませんね。一見すればまともになったのかと思えば、拍車がかかって更に性質が悪くなって」 鉢屋が皮肉に顔を歪めて笑いながら数歩前へ進み足元にあった石をコツンと蹴り飛ばす。 その墓の主である“穢れ”が鉢屋の行動に怒り、激昂のまま鉢屋の足に絡みつくが直ぐにその姿は四散して靄となって消えてしまう。 「やはりあれはお前だったか鉢屋」 立花が、笑みを深め至極楽しげに言葉を吐いた。 一瞬鉢屋は不可解そうに眉を潜めたが直ぐにハッと何かに気がつくと悔しそうに顔を顰めて目の前の先輩を睨みつける。 「なんですか先輩、あれが私だって確信なくカマかけたんですか」 事の真相に気づき、一杯喰わされたことを悟った鉢屋が不機嫌そうに唇を尖らせて爛々とした目で立花を見ると、彼は愉快そうに肩を震わせ「そう言うことかな」と茶化しながら笑う。 「私が六年になるまで奴のことを探っていたのに全くそれらしい者が見当たらない……薄々お前ではないかと勘ぐっていたが、証拠は無い。そして今日たまたまお前がここにいたから少し話してみただけさ。するとまぁ大あたりだったわけだ」 「あの子供が忍者に向いて無くて学園を去ったなんて可能性は考えなかったんですか」 「まさか」 鉢屋の言葉に一拍の間も置かず立花は否定の意を表す。 疑い深く立花を見る鉢屋に、彼は長く艶やかな黒髪を揺らして鉢屋の元へと歩み寄る。 「あんなにも死臭を臭わせている奴が忍者の学園を去って何処へ行くというのだ?」 「逆に私は真っ先にあの子供――仙蔵はこの学園を去ると考えていましたよ」 鉢屋の切り返しに立花仙蔵の片眉を釣り上がる。興味深そうに彼の間合いの一歩手前で立ち止まり立花は「ほぉ、何故だ?」と面白うに問い返した。 「だってあの子供にしてみればこの学園は緩く生ぬるい。狂気に飢餓して外へ飛び出しているものだと思っていました」 鉢屋はなんてことはなさそうに言って、相手が年上の先輩であることも気にせずに「それがまぁ、こんな人間になって……」と残念そうに顔を顰めてみせた。 そんな後輩に対して立花は愉快そうに豪快な笑いを飛ばして、腹を抱えて笑いだす。それは作法委員長でもある立花仙蔵にしてみればとても珍しい笑い方だった。おかげで鉢屋は本日何度目かの驚きを目の前の立花に対して抱くこととなる。 眼尻に涙を浮かべ洪水のように笑いを溢れさせていた男が漸く一息ついて顔を上げ、まっすぐに鉢屋三郎を見据えて「お互い様だろう?」と艶やかな笑みを零して微笑んだ。 |
sozai(http://swordfish.heavy.jp/blue/index.html)
091112